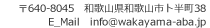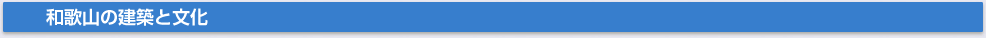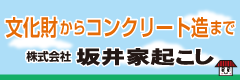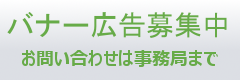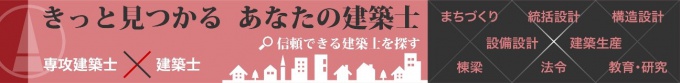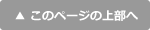和歌の浦あしべ庵(旧福島嘉六郎邸)
和歌の浦あしべ庵(旧福島嘉六郎邸)
施設概要
敷地面積 2,683.79㎡
規模・延べ床面積 既存母屋棟 木造2階建て 206.38㎡(昭和4年建設)
既存離れ棟 木造平屋建て 91.97㎡
その他既存建物 蔵、待合
新設トイレ棟 木造平屋建て 34.47㎡ (令和5年竣工)
- トイレ棟・駐車場整備
設計 株式会社田渕建築設計事務所
施工 アズマハウス株式会社
- 母屋棟屋根改修・外観修景
設計 株式会社キューブ建築研究所
施工 株式会社蔭山組
- 離れ棟耐震改修
設計 株式会社キューブ建築研究所
施工 株式会社藤本水道
神亀元年(724年)に即位した23歳の聖武天皇は10月和歌の浦に行幸し、その景観に感動しこの風景を末永く守るよう詔を発したと言われています。2024年である今年はそれから1300年の節目にあたり、10月27日には「和歌の聖地・和歌の浦 誕生千三百年記念大祭」が盛大に行われました。それに先立ち玉津島神社の隣に位置する旧福島嘉六郎邸が整備され、和歌浦周遊の拠点となる施設「和歌の浦あしべ庵」として今年9月に開館しました。
福島嘉六郎は明治8年に生まれ、和歌山県の捺染(なっせん)業発展に貢献し和歌山綿布株式会社を設立した実業家であり、書画骨董の蒐集・鑑定、茶の湯にも興じる趣味人でもありました。また和歌浦は風光明媚な景勝地として王侯貴族や文人の憧れの地であり、その一等地に昭和4年(1929)、福島嘉六郎の別荘として建設されました。この施設は、荒々しい岩肌の伽羅岩(きゃらいわ)を持つ奠供山(てんぐさん)を借景とし、島のある池を配した池泉回遊式庭園と近代和風建築が一体となったものです。
母屋は木造2階建、入母屋造、瓦葺、軒先銅板葺。数寄屋造りの趣きが濃く洗練された意匠です。基礎は庭園の石組みに柱建てをし、懸造り風の外観を持ちます。離れは木造平屋建て、寄棟造、瓦葺。間取りとしては玄関を上がり左に和室六畳、右手に廊下を介して六畳二間の続き座敷が設えられています。敷地北側は奠供山に向けて高くなり、玉津島神社と地続きとなっています。その場所は一段高い場所から庭園と和歌浦の風景を見渡すことのできるビューポイントとなっています。元々こちらには茶室がありましたが焼失してしまい、少し下ったところに待合のみが現存しています。また敷地西側には力強く岩塊から幹が張り出すクロマツがあり、地元の小学生から「一生松(いっしょうまつ)」と言われ親しまれているそうです。
今回「和歌の浦あしべ庵」として整備するにあたり、三期に分けて工事が行われました。
一期では屋外トイレの新設や駐車場の整備など、二期で母屋棟の修繕及び外観修景、三期で離れ棟の耐震改修工事が行われました。耐震改修は限界耐力計算によって行われ、間取りにほぼ変わり無い状態で耐力壁が設けられました。離れ棟は観光案内、歴史文化の情報発信、体験交流、滞在休憩などのため利活用できるよう改修され、その内部は襖紙も当時のままであるなど、昭和初期の邸宅の雰囲気を味わうことができます。室内には和歌浦の古い風景写真など様々な展示が行われており、土日祝には“NPO法人 和歌の浦 自然・歴史・文化支援機構”の方々が常駐し、訪れる人に歴史や観光スポットを案内してくれるそうです。
またこちらのNPO法人は「名勝和歌の浦クリーンアップ」という活動を10年以上前から行っており、この施設も継続的に清掃や草刈りをしていたそうです。このような地域の力があってこその旧福島嘉六郎邸の再活用であることを、今回の取材を通じて大いに感じました。付近には玉津島神社、鹽竈(しおがま)神社、不老橋、和歌浦の干潟、妹背山、片男波など古くからの名所が多く存在します。山部赤人の万葉の歌に詠まれ、歌川広重の「六十余州名所図会」にも描かれた風景、ぜひ「和歌の浦あしべ庵」を拠点として散策してみてください。
【会報誌きのくにR6年12月号掲載】
情報・出版委員 南方一晃